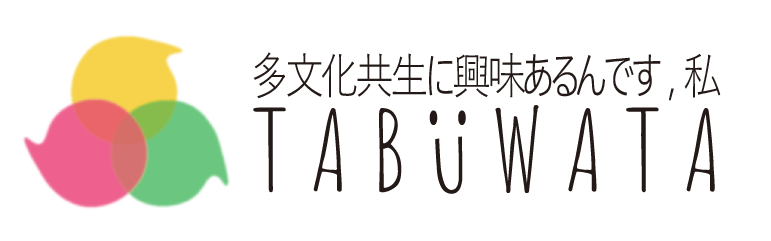TABUWATA(たぶわた)の設立は2021年ですが、その前身となる活動は2012年にさかのぼります。2012~2018年度の〈文化庁委託事業期間〉、2019年~2020年度の〈自主活動期間〉を経て、2021年3月11日にTABUWATAが発足しました。
2012~2018年度〈文化庁委託事業期間〉
始まりは、現共同代表の栗又が、2012年に「やさしい日本語」を普及することを目的とした文化庁委託事業を受けたことでした。やさしい日本語をどうやって普及させるのか模索するなかで、身近なニュースなどをテーマや教材に使ってもなかなか人が集まりませんでした。そうしたなか、偶然知り合った動物園の園長からアルパカを貸し出してもらえることになりました。アルパカがいるだけで、人を集めることができ、いっきにやさしい日本語の普及にもつながりました。
日本語教育とは関係がないと思っていた力を借りることで、日本語教育を促進できる可能性を実感できたと同時に、日本語教育から一歩、地域社会に踏み込む重要性を痛感した出来事でした。
しかし、すぐに日本語教育関係者、自社の関係者だけでは、新たな協力者を得ることに限界も感じました。そこで、当時すでに知り合いだったもう一人の現共同代表である坂本に相談したことで、一緒に活動するようになっていきました。
日本語教育だけでは「日本語」を教えられないジレンマ
文化庁委託事業では、FMラジオで 身近なニュースをやさしい日本語で伝える番組「やさしい日本語地域ニュース」を企画・実施しました。しかし、日本語学習者から質問を受けても、専門知識が必要なことも多く、日本語教師である栗又は、日本語学習者が生活者として必要とする情報を教えられていないことに疑問を抱くようになりました。
そこで、日本語学習者が専門家へ直接質問し、日本語教師がやさしい日本語で通訳する番組を企画・実施ししました。すると、専門家自身が日本語を調節して、やさしい日本語を修得していきました。当時、文化庁委託事業の趣旨は、あくまでも日本語ができない外国人がやさしい日本語を修得するための普及を目指していましたが、日本人が外国人とコミュニケーションを図るために修得すべきなのがやさしい日本語なのではないかという考え方へと変わっていきました。
また、生活者としての日本語を教えるには、暮らしに関わるさまざまな専門家たちとつながる必要性も高まりました。しかし、そうしたネットワークももっていませんでした。
生活者として捉えられていない外国人
当時、自治体シンクタンクに勤務していた坂本は、さまざまな地域の団体とも関わっていましたので、つなぎ役となっていきます。
生活者としての外国人をつなげるべき機関・組織を検討
- とちぎボランティアNPOセンターや 宇都宮市社会福祉協議会、看護専門学校 などへ
- しかし、いざ既存の組織とやさしい日本語の普及をつなげようとすると、当時、最初の反応は「うちは外国人を専門としていません」と言われることもしばしばでした。
社会的変化
- 専門家のやさしい日本語への関心が高まる。
- 学生の関心や意識が高まる。
- 参加した外国人住民の自信や意欲が高まる。
外国人住民が抱える問題を地域へ届けるための工夫
新たな疑問や気づき
- 専門的な話や生活問題がテーマだと、面白さに欠け、外国人住民に関心のない人たちを引きつけられないのではないか。そのためには、日本語教育から一度離れてみてはどうか。
- 青年会議所の方から「楽しくて馴染みやすいテーマの活動が必要」という意見をもらう。
- にほんご・しち・ご
日本語学習者の生活の様子や心情を詠った川柳を、詠った本人から紹介してもらう番組を企画・実施。
「じてんしゃに のれるとしより ものすごい」全国FM放送界JFN賞2017「地域賞」受賞
消費型音声情報をどう地域へつなげるかを検討
- 行政や研究活動にいて、報告書を作成することは一般的。活動を形に残す必要性を提示。
社会的変化
- ラジオを聞かない人たちや普段外国人と関わりがない人たちへ伝えるツールとなり連携拡充へつながる。
2019年~2020年度〈自主活動期間〉
日本語学習者が主役になれる場所・主役になるべき場所
新たな疑問や気づき
- 「にほんご・しち・ご」で自らが詠んだ川柳を紹介する人たちが楽しそうにしている様子を目の当たりにし、もっと日本語学習者が主役になれる場をつくれないか。
あなたの隣の外国人
- コミュニティFMミヤラジへ移行し、住民としての外国人自身が番組内容を決め発信できる番組を企画・実施。
コミュニティFMの役割である災害時の情報伝達と外国人住民の主体的な参加について検討
- ミヤラジ設立の想いとの重なり、文化庁委託事業としては終了したが番組は継続。
- 外国人住民が支援される/する側として関わるための場を模索
社会的変化
- ミヤラジスタッフの理解の深まる。
- 宇都宮市総合防災訓練での多言語放送が実現し、地元新聞にも掲載される。
- 災害時緊急対応やフードバンク活動を行うボランティア団体から連携の申出を受ける。
防災を中心にしたら見えてきたこと
TABUWATA:ミヤラジやVネットとの協働
- 日本人住民と外国人住民の双方の防災意識の醸成を目的に、外国人住民が母語で防災知識を発信する5分番組を企画・協働。
- 3月11日には、一日中いろいろな番組に外国人が出演する特別番組を企画・協働。
新たな疑問や気づき
- 外国人住民が災害時に身を守るための日本語の必要性を再確認
- 日本人の「やさしい日本語」≒日本語調整力の必要性と重要性
- 東日本台風(台風19号)や新型コロナウイルス感染拡大に伴う情報発信と支援体制の検討
- 地域の“多文化”防災訓練の事前学習として勉強会を実施することで協力。地縁組織としての国際交流会の可能性。
- 学生がつくるミヤラジ「がけっぷちラジオ」にゲストとして招かれる。
- 防災マネジメント、福祉社会学など他分野の研究者との連携。
社会的変化
- 自治会役員たちが「やさしい日本語」にチャレンジする。
- コロナ禍におけるフードバンク活動で、外国人住民を意識した配慮が自然発生。やさしい日本語での情報発信へ。
残された課題とこれから
- 外国人自身が住民として地域へ参加する意識をどう醸成するのか。
- 散住地域でどう共通認識や取組を浸透させるのか。
- コロナ禍で、誰が情報を“つなぐ”のかという課題に直面。