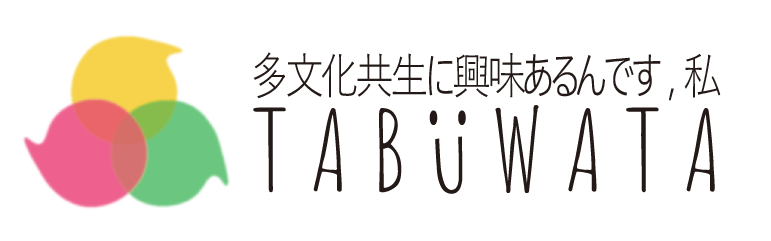多様な価値観や文化は社会を豊かにする。TABUWATA(たぶわた)は多様性に含まれた「違い」を大切にし、それを誰もがワクワクするような希望や可能性につなげることに夢中です。この実感と信念を基軸に、行政や企業、NPOや地域等と日本社会の多様化をめぐる課題に向き合い、日本人と外国人が共に主体的な構成員として、さまざまな取組を行っています。
| スピリット | 代表あいさつ | 団体概要 | 設立背景(準備中) |
大切にしていること~TABUWATスピリット~
多文化共生をテーマに何かに取り組むことは、どこか特別で難しいことのように受け取られることが少なくありません。しかし、私たちが「TABUWATスピリット」と呼んでいる以下3つのことは、多様化する日本社会においても暮らしやすい環境を整えるうえで大切なことだと考えています。
1、 安心して「違い」を出せる環境をつくる。
異なる価値観や意見を安心して表現できることは、多様化する社会にとってとても重要です。多数を占める価値観や意見とは異なっていることにこそ、これからの時代を生き抜く新たな価値や仕組みが創造できると思うからです。
2、 出された「違い」に対して折り合いをつける。
残念ながら「違い」は時として誰しもが心地よいものだとは限りません。誰かにとって心地よくても、他の誰かにとって心地よくないこともしばしばです。人にはどうしても譲れない、譲りたくないこともあります。それはに日本人同士であっても、日本人と外国人であっても同じです。”心地よくない”「違い」と出会えた時こそ、多文化共生を進展させる絶好の機会と捉え、そうした場面で、折り合いをつけることが大切だと考えています。
3、 これらの実現のため、役割による“力の勾配”を生じさせない配慮と工夫をする。
日本人は往々にして「違い」に対して折り合いをつけることを苦手としているように思います。しかし、ますます多様化する社会において、どのように折り合いをつけるのか、その技能は、これからの教養的スキルといっても良いでしょう。
その具体的な方法の一つが、役割による力の勾配関係をつくらない、ということです。教えるー教えられる、助けるー助けられるといった役割分担は、知らず知らずのうちに「違い」を出しにくくし、折り合いをつける機会を奪うからです。対等な関係のなかでこそ、相互に「違い」と向き合うための対話を生み出せるのではないでしょうか。
そうは言っても、こうした「違い」によって摩擦が生じる現場やそれを乗り越えた経験がある人たちは、まだまだ少ないのが現状です。そこで、自分自身に次の2つの質問をしてみてください。きっと見落としている何かや足りない何かに気がつくはずです。
そのやり方は名前を呼び合える関係づくりにつながりますか?
日本人もしくは自分の感覚だけで判断していませんか?
このようにして、今では、このTABUWATスピリットの普及もまた、私たちの大切な取組の一つとなっています。
初めてTABUWAの活動に参加する方々には、このスピリットを踏まえたうえで、どうやってそれを実現させるのか、その方法を自由に考えてもらっています。メンバーの誰かが提案し、それを他のメンバーがサポートしながら実現する。こうして常にたくさんのアイデアが出され、どんなに多文化共生に関する取り組みに不慣れな方であっても、主体的に活躍することができます。
何よりもまず、活動に関わる私たちが、年齢や国籍に関係なく対等な関係を築き、それぞれができること、得意なことを活かして、同じ目標に向かって折り合いをつけながら実践し、成功体験に変えていくことを重視しています。
代表あいさつ
多文化共生という言葉が広がり、多くの人にその言葉が認知されるようになりました。ただ、この言葉が示す世界を想像し、理解するのは簡単なことではないと感じています。
しかし、その状況はすでに私たちの隣にあり、それを受け入れ、理解し、暮らしていかなければなりません。多文化共生の活動をしている私たちにもわからないことだらけ。だからこそ、多様な人々と繋がり、私たちもその言葉が示す世界を知りたいと思っています。
他者を理解し、お互いが気持ちよく暮らしていく。こんなまちづくりを、人に伝え、人と人をつなげ、実践していく。それがわたしたちの活動です。

共同代表 栗又 由利子
(株式会社きぼう国際外語学院・教務主任)
多様性は、困難と機会の両方をもたらすものだからこそ、一人の人間としてだけでなく、社会全体としての成長をもたらすことができる可能性をもつのだと思います。多様性がもつ可能性を信じ、活かしていける社会の構築。それは、多文化共生に関心がない人々や外国人嫌悪をもつ人々を含んだ、社会全体で成し遂げなければなりません。
その実現には、政策だけでなく、私たち一人一人が身近なところから、日々の積極的なふれあいや対話の場を増やしていくこと、そしてちょっとしたトラブルをも大切にしていくことが重要です。偏見は誰にでもあります。しかし、それが「無自覚な」差別や排除につながらないよう、私たちは、私たち自身の在り様を見直していくことが大切です。
TABUWATAでは、多様性がもつ可能性を信じ、新たな価値の創造を見据え、豊かで暮らしやすい地域づくりを目指します。

共同代表 坂本 文子
(福岡工業大学教養力育成センター・助教)
団体概要
| 名称 | TABUWATA | |
| 事務局所在地 | 〒329-2142栃木県矢板市木幡866-3 | |
| TEL | 0287-43-6008 ※自動応答になっていますので、メッセージを残してください。事務局からかけなおします。 | |
| FAX | 0287-43-6008 | |
| tabuwata.tochigi@gmail.com | ||
| URL | https://tabuwata.org | |
| 代表 | 共同代表 栗又由利子 共同代表 坂本文子 | |
| 設立 | 2021年3月 | |
TABUWATAは、2021年3月に設立された主に栃木県内を中心に活動する多文化系まちづくり団体です。現在、会員数85名(2025.3.31、内役員9名)から成る任意団体です。役員数は、会長2名、副会長2名、幹事2名、会計1名、監事2名の合計9名に加え、顧問として団体運営の経験が厚い2名に入っていただいています。役員や顧問には、計5名の海外ルーツの方も含まれています。
TABUWATA(たぶわた)という名称は、「多文化共生(たぶんかきょうせい)に興味あるんです、私(わたし)」の略です。多文化共生を自分ごととして考えて欲しいという想いが込められています。
私たちは、TABUWATAスピリットを大切にしながら、日本人と外国人のつなぎ役となることを使命としています。「つなぐ・伝える・実践する」をキーワードに、日本人と外国人だけでなく多様な背景をもつ人々が対等な関係を築き、共に考え、共に活動できる地域社会の実現を目指します。
設立背景
(準備中)