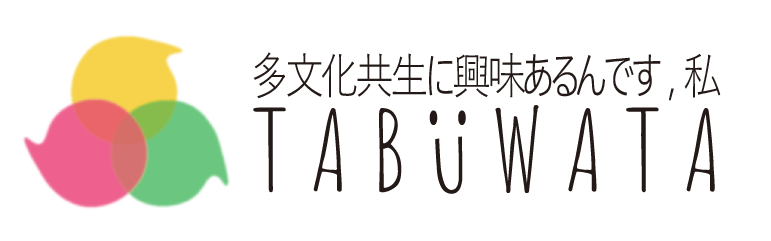【活動報告】3.11ミヤラジ特別番組「外国人住民と災害に備えるラジオ」放送!後編をお届けします。
今回は、13年前の震災発生当時を振り返りつつ、「今」考えていることについて語り合いました。
【後編】
後半は、前半から引き続きサントスさんとクンさんに加えて、お子さんの卒業式から駆けつけてくれたベトナム出身のアインさんの3名が出演。
まずは、今年度TABUWATAが取り組んだ防災の活動について簡単に紹介しました。
・外国語ラジオの放送
現在ネパール語、中国語、タイ語の3言語による外国語番組をミヤラジで放送中で、災害時を想定した日ごろから外国人住民が聞いても楽しい番組作り。外国人住民自身が主体となって行える環境と関係づくり。
・防災勉強会の開催
地震や大雨・強風・火事、また非常食を作って食べることを「実際に体験」する勉強会を開催。
アインさんは、防災勉強会に参加した理由を「死にたくないから」と答えてくれました。それはとてもシンプルなことですが、この活動は命を守るためにやっているんだということをより強く意識するきっかけになった言葉です。この日のラジオでも、後半全体を通してキーワードになっていました。
そして「今後やりたいこと」をじっくり語り合っていただきました。
アインさんからは夜間の防災訓練。停電や断水が起きたとき、真っ暗な夜にどれほどのことができるのか、何もできないのか体験しておきたい、というお話が。
それに対してサントスさんから、ネパールには電気が通っていない地域多いから、火起こしが得意だという提案があり、みんなが得意を持ち寄ってやれたら楽しいねと盛り上がりました。
サントスさんがやりたいことは、命を助けたいときにどうすればいいのか、救急救命の講習を受けてみたいとの話がありました。
それに対してクンさんから、AED講習についてのアイデアも。機械に書かれている日本語が難しい、読めない、音声が早くて聞き取れないといった課題も挙げられました。
音声の日本語は、たとえそれほど難しくない日本語を使っていたとしても、早口で話されると聞き取れないとのこと。ゆっくり話すとか、字幕をつけるとかの対応がされたらもっとわかりやすくなること。
多言語を表示したり、QRコードで翻訳が表示されたりする方が簡単ならそれもいい、というようなアイデアもたくさん出てきました。
2:46をはさんで…
「今、ここで、私たちができること」について話していきました。
日本語をもっと勉強するということは3人とも共通。
サントスさんからは、防災バッグを準備すること。その後の行動もイメージして準備する。スマホが使えなくなることもあり得るので、ラジオも準備する。普段からラジオを聞く習慣を身に着けておく。キーワードは「もの」。
アインさんからは災害をテーマにした学びの場には積極的に参加すること。やっていいこと、やってはいけないことなど。ベトナムとは違うこともある。知識をしっかり身に着ける必要がある。キーワードは「知識」。
クンさんからはスマホの災害シミュレーションアプリなどを活用して、行動をイメージすること。心の準備をしておく必要がある。キーワードは「心」。
「もの」「知識」「心」の準備。これらを、日本人と外国人も一緒に取り組むことがとても大切なことで、お互いのことを思いやりつつ、相容れない部分については折り合いをつけて、互いに助けたり助けられたりできる関係を築いていくことが重要なことだと皆で再認識しました。
最後に、アインさんから「やってみたいことを、他で言うのは恥ずかしいが、TABUWATAなら恥ずかしくない!」と嬉しい意見がでました。
【まとめ】
1年前のこの番組で、防災について学ぶ場を一緒に作ろうと約束していました。そして実際に防災勉強会を開催してみて、ますますやりたいことが増えました。
13年前と今、変化していることも多くあります。TABUWATAのできること、やらなければならないことを、バージョンアップしながら続けていくことが大切と信じ、一歩ずつ進んでいきたいと思います!